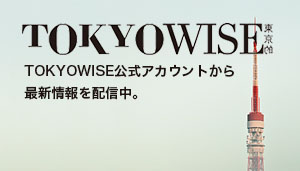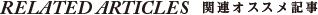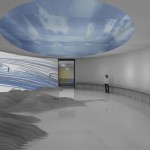2016.04.06
東京の至る所で行われている再開発の工事。2020年の東京オリンピック開催も決まり、その勢いはますます加速しているのが肌で感じられる。しかし、既存の街をリセットし、新たに作られた街や商業施設はどこも同じ様相で、何の面白味も色合いもない。一方、不愛想な主人が美味いコーヒーを淹れてくれる喫茶店、だみ声で威勢を張る八百屋、毎夜煙がもうもうと立ち上る焼鳥屋など、東京らしい路地裏の光景は日に日に失われている。一体、東京という街は何をゴールとして、これらの都市開発を行っているのだろうか。
「東京が抱えている問題は、都市開発だけでは解決できないと私は思っています」と語るのは、UDS株式会社の黒田哲二氏。同社では、住みたい人が集まり共同で住まいを作る「コーポラティブハウス」事業や、リノベーション物件を活用した商業施設やホテルなどの企画、設計、運営など、時代にフィットした様々なプロジェクトに取り組んでいる。また、かつては建築家を目指して隈研吾氏に師事し、森ビル株式会社でエリア開発に従事するなど、その多様な経験値を持つ黒田氏に、東京の都市開発の現状について話を聞いてみた。

経済成長、オリンピックありきの開発
戦後、東京に復興をもたらした1964年開催の東京オリンピック。首都高速や東海道新幹線などのインフラ整備をはじめ、現在ある東京の都市構造の礎を築く大きな契機となったことはいうまでもない。では、2020年に向けて東京はどのような変貌を遂げるのだろうか。
「大会施設やインフラを除いて、東京という街をどうしていくのかという公の指針は、大枠でしか提示されておらず、街の開発自体は民間企業に任せきりです。例えば、ロンドンでは荒廃した東部エリアにオリンピック・パークを整備することで、格差や治安を改善していこという計画が行われました。それは“legacy(遺産)”として、結果的にロンドンの街全体をボトムアップした成功例だと思います。しかし、東京はそこそこ便利ですし、治安もそこまで悪くない。底辺には色々な問題もありますが、都民にとって一丸となれるような課題がないことこそが問題なんじゃないかと思うんです」
たしかに、欲をいえば後を絶たないが、東京で暮らしていて不便を感じることは少ない。都知事選でも大論争になるようなテーマもない。しかも、およそ1300万人の東京都民のうち約半数が地方出身者であるこの街は、ローカルに比べて総意としての“地元愛”に欠けているのかもしれない。
では、その課題がないまま推し進められている再開発ラッシュというのは、何を目的に、誰のために行われているのだろうか。
「結局は土地や建物の所有者にとっての利回りのため、投資をしてどれだけ収益性を上げられるのかという観点から開発は行われています。土地の価値を最大限に活かすには、開発してまとめた土地を作った方がいい。要するに、駅前の良い土地に商店街があったとしても、そこをすべてスクラップして駅直結のビルを作ることで、その土地から最大の収益を生むことができます。これまで、日本の企業がどんどん増えてオフィスが不足し、住宅もどんどん売れるからこそ、この論理は成り立ってきました。しかし、開発には長年かかるため、タイムラグがかなりあります。数十年前の経済成長が右肩上がりの論理で考えられた都市開発が、いまのような低成長時代になってくると違和感や温度差を感じてしまうんでしょうね」

箱物だけでは文化は生まれない
近年でも屈指の大規模開発となった「虎ノ門ヒルズ」のプロジェクトにも携わってきた黒田氏。ソーシャルビジネスで注目を集めるグリーンズや、ハイセンスなモノづくりを手掛けるランドスケーププロダクツなど高感度な人々に声を掛け、ヒルズ周辺の空き地や未使用の建物を活用したカフェやギャラリー、ショップなどを展開し、虎ノ門という街自体への集客を図った。
「ビルをいきなり作っても渇いた土地に苗木を植えるようなもので、土壌が豊かじゃないと森も上手く育ちません。文化を育てるという姿勢が開発側にない限り、やはりその土壌は育たないと感じました」
外国人観光客が年々増加しているいま、観光都市として東京の魅力を考えてみると、現在の画一的な都市開発が果たして本当に正解なのか、ますます疑問に感じてしまう。もし、自分が外国人観光客なら、丸の内や虎ノ門には決して行かない。やはり、浅草や原宿、新宿などの東京らしい混沌とした街並みや、個人商店の集合体にこそ、その街の文化や人を感じられるのではないだろうか。黒田氏は人が感じる街の魅力を左右するのは「冗長性」の有無だという。
「パソコンはシステムをきっちり組み上げるだけでなく、冗長性という遊びの部分がないとうまく機能しないんですが、それは都市においても同じことなんじゃないかというテーマを、学生時代に研究していました。都市開発をする時、大きな四角い建物をただ並べるだけでなく、傍らに小さな商店街や少し違和感のある建物などがあるとその街の冗長性が増し、より機能するということです。例えば、渋谷という街は地形に特徴があるため、河の流れや土地に合わせた不整形な区画ができ、建物や街に独特の雰囲気や面白味があります。逆に京都などは碁盤の目のように一見きっちり区画されていますが、細かい路地が張り巡らされていることで多様性が生まれているんだと思います」
渋谷に迫るジェントリフィケーション
そんな冗長性が高く魅力的な街だという渋谷も、現在、開発の真っ最中。渋谷駅周辺の都市計画の行方について、黒田氏に聞いてみた。
「計画全体を把握しているわけではありませんが、利便性の観点で駅からフラットな平面を広げることになると思われます。そうすると、すり鉢状の地形を大きな床で覆う形となるので、街の冗長性は失われるでしょうね。また、周辺の賃料単価が上がることで個人商店は参入が難しくなってくるため、大手チェーンの飲食店やコンビニエンスストアなど想定できるテナントが決まってくるので、やはり多様性のない街にならざるを得ないでしょう。どういう街を作りたいかではなく、数字ではじき出されたものの積み重ねが、いまある東京の姿なんだと思います。これからの低成長時代にこそ、お金の理論ではない価値を見出していくことが、魅力的な街を作る上では重要になってくるんではないでしょうか」

スクラップ・アンド・ビルドが生んだ混沌とした都市に暮らす私たちにとって、歴史的建造物を除いて守るべき建物はないのかもしれない。しかし、そこで生まれた街の文化や香りまで奪ってしまう都市開発に、やはり私は賛同できない。
前途のロンドンにおける開発も、その余波として起こったジェントリフィケーション(Gentrification/貧困層が多く住む地域にミドルクラスの人々が流入することで、家賃相場が上がり元々の住人たちが流出し、地域特性が失われる現象)が問題となっているが、東京の都市開発も同様の現象を生んでいる。乱開発で続々と生まれる都心の高層オフィスで働く人やタワーマンションに暮らす人々のライフスタイルを想定した街から、その地域文化を育んできた住人や個人商店たちは排除されていく。渋谷にしてものんべい横丁や円山町界隈など昔ながらの風情を残すエリアは、現状では再開発計画から外れているが、これまでの開発エリアを鑑みると、周辺の地価相場の上昇に耐えきれるか難しいところだ。こうしてソーシャル・クレンジングされていく無味無臭の街をギュッと寄せ集めた東京の未来像に、一体誰が魅力を感じるのだろうか。
日々変貌するこの街において、何を都市の象徴として、何を未来に残していくのか。東京のユーザーである私たち自身が、その価値を見出していく必要があるのかもしれない。
黒田哲二(くろだ・てつじ) 1977年神戸生まれ、東京育ち。東京大学工学部建築学科卒業後、隈研吾建築都市設計事務所を経て、2005年より株式会社都市デザインシステム(現UDS)にて企画開発業務を担当。2008年より森ビル株式会社にて、虎ノ門ヒルズ開発業務に携わり、「リトルトーキョー」「Curator’s Cube」「グッドモーニングカフェ&グリル虎ノ門」「アーバンリサーチドアーズ虎ノ門」などのエリア活性化を手がける。2015年よりUDS株式会社へ復帰。「企画」「設計」「運営」を強みとする同社の「企画」の柱として、国内外問わず、新規プロジェクトに奔走している。