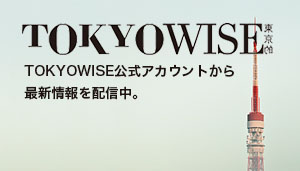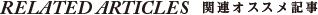2015.01.26
- tokyoPop
-

episode#02
カジュアル・ニヒリズムの台頭~恐ろしくクールでリッチだった10代たち
1987~1991年。それは言うまでもなく「バブル80’s(バブル・エイティーズ)」として記憶されるべき時代であり、特にこの時期の若者文化の主導権を握った20代の社会人(あるいは年上と遊ぶ女子大生)たちは史上最もリッチな青春を送ることになった。
一方でepisode#01で描いたように、マスコミの情報発信や大人の提供場所に踊らされるのではなく、自分たちの手で流行や現象を起こそうとする一部の付属/私立校に通う高校生による立ち振る舞い=「クチコミ」(*1)「カジュアル・ファッション」「チーム/パーティ」といったものは、この時期により拡大・洗練されていく。
その主な原因は二つ。まずは団塊ジュニア世代(*2)が高校生になり始めたこと。つまり、高校生人口の増加。この世代で初めて1~3学年が占められた1989年は、全国で約564.4万人(文部科学省調べ)もの高校生がいてその数はピークに達した。そして経済景気上昇による若年層の消費力の飛躍的な伸び。
TOKYOに出入りする高校生であれば、誰にでも渋谷の青春を謳歌するチャンスはあった。さらに年収や職業などのタテ価値観に惑われる社会人に比べて、3年間期間限定という平等のヨコ価値観を持つ少年少女たちには情報伝達のスピード化が初めから備わっていた。
大学生/女子大生や社会人/OLの流行がファッション雑誌主導であるのに対して、TOKYOの高校生の流行は一部のオシャレな高校生が先導する。この明確な違いこそがヒップとスクエアの境目と言えた。「最初の80年代」に強く漂っていたポップな感覚は、「バブル80’s」では徐々にクールな感覚へと変換していったことも確かだろう。
1987年は前年から兆しがあった「アメカジ」(*3)と「パーティ」の大ブームが起こった。背中にチーム名がデザイン(*4)された揃いのウインドブレイカーやスタジャンなどのチームオーダーものも定番化。1988~1989年はカジュアル・ファッション第2弾「渋カジ」(*5)が発信され、山の手エリアの大学生にもキャンパス・ファッションとして共有されて流行語にもなった。1990~1991年には第3弾「キレカジ」(*6)が登場。ラルフ・ローレンの紺ブレや胸にポロの刺繍が入ったオックスフォード地のボタンダウンシャツが制服化して、「ローレニズム」(*7)に傾倒する高校生が続出した。
同時期の20代社会人がジョルジオ・アルマーニなどのイタリアン・ブランドを着用して銀座や六本木のナイトライフで狂乱の「アルマーニズム」を毎晩謳歌していたことを思えば、渋谷のアフタースクールに集う高校生の方が恐ろしく大人びていたのかもしれない。それはラルフ自身が憧れたニューイングランドの森林の微妙な揺れにも似た、非常に落ち着いたハイスクール・スピリットの極致だった。彼らの親の多くはアメリカナイズされた団塊世代の成功者だったので、自信と余裕に満ち溢れた家族の絆を象徴するラルフの服なら、喜んで認めて買え与えたのだ。
また、一大勢力となった大学デビュー組(*8)に見向きもしない付属校上がりのリッチな大学生たち(「最初の80年代」にTOKYOで高校生活を送った者たち)にも、この「ローレニズム」はシンクロした。1989年に公開された映画『レス・ザン・ゼロ』(*9)は彼らの間でカルト化。この作品で描かれた「カジュアル・ニヒリズム」(*10)は“ハイスクール・スピリット2.0”そのものだった。
こうした光景は延々と続いていくように思われた。そういう計算だった。しかし、バブル経済が崩壊して一つの時代が終わろうとする時、高校生も若者社会も何者かによってあっけなく変えられてしまう。だがその前に語らなければならないことがある。土曜の夜、渋谷のストリートを舞台に描かれた「センター街チーム現象」だ。
(episode#03 へ続く)
(*1)伝達される場所として、渋谷はジャック&ベティ、トップドッグ、ソーホーズ、プライム、アンナ・ミラーズなど。六本木はストロベリーファーム、イタリアン・トマトなどが溜まり場となった。自由が丘も重視され、バターフィールズ、ラズベリーヒル、カスタネットなどが使われた。広尾のホームワークスや都立中央図書館、麻布十番の夏祭り、カジュアル・ファッションを売るセレクトショップ、109のソニプラ、ビリヤード場やディスコも好まれた。
(*2)マーケティング的には1971~1974年生まれを指す。文字通り、第一次ベビーブームである団塊世代の子供たちで、第二次ベビーブームでもある。1990年は高校中退者数がピーク、1991年は帰国子女数がピーク。ちなみに現在の高校生人口は約320万人。
(*3)アメリカン・カジュアルの略。
アディダスやケイパやリーボックのスニーカー、ジョッパーズ・パンツにハイソックス。あるいはジーンズにレッドウイングやチペワのエンジニアブーツをイン。MA-1ジャケット、NFLのチームシャツやラガーシャツ、ポロシャツ、SASのバッグも主要アイテム。映画『トップガン』や『プラトーン』、デム・ジャム系ヒップホップ音楽も影響した。また、同時期にはスケボーのリヴァイヴァルも起こっていて、ネルシャツやロングとショートスリープの重ね着などが流行。彼らはスラッシャーと呼ばれて音楽との相性も良かった。『バック・トゥ・ザ・フューチャー』でのスケボーシーンが発端という説あり。
(*4)元祖のファンキースをはじめ、ストリート・エンジェルス、ノーティーズ、フィクサーズ、アリゲーターズなどが雑誌Fineで「アメカジチーム」として紹介された。
(*5)渋谷カジュアル、渋いカジュアルの略。カジュアル・ファッションにヨーロピアンテイストを加え、高級ブランドも一品取り入れたスタイル。初期の渋カジはピカデリーやシピーなどのインポートジーンズ、デッキモカシン、ストライプシャツ、ヴィトンのバッグが定番。女子はソバージュ髪が多かった。大学生層にも広まり、女子大エレガンスに対する共学カジュアルの位置付け。渋谷センター街チーム現象が一般的に認知されると、彼らが渋カジと呼ばれたりもした。
(*6)キレイめカジュアルの略。
こちらもチノパンやマドラスチェックのパンツ、シャンブレーシャツ、ペニーローファーやワラビーやデザートブーツ、ターコイズブルーのアクセなど定番アイテムは尽きなかったが、マストアイテムだったのが紺色ブレザー。ブランドはラルフ・ローレンに意味があった。ちなみに第4弾カジュアルは「デルカジ」(モデル風カジュアル)。
(*7)同時期に描かれたセンター街チームのハードなアメカジ、スケーターやサーファーなどのストリート・ファッションに対する保守的な動き。ラルフ・ローレン曰く「ポロはファッションではなくスタイルだ」。ラルフを着ることは一つの伝統的かつ特権的な世界に入ることを意味していた。広告は服そのものよりもその服を着る者たちのライフスタイル・イメージが強調されている。ちなみにラルフ・ローレン自身はWASPではなくユダヤ人。
(*8)当時、過酷だった大学受験を通過してキャンパス・ライフに入った者たち。日本全国から集まるため、圧倒的人数。大学生になってようやく遊ぶこと/群れることがスタートできたので、高校時代に同様の遊びを済ませていた付属校上がりの内部進学者はカルチャーショックだった。1968年生まれの女流作家・鷺沢萠は短編「ティーンエイジ・サマー」でこのあたりの温度差を描いていた。
(*9)アメリカの文学ムーヴメント「ニュー・ロスト・ジェネレーション」を代表する作家ブレット・イーストン・エリスによる同名小説(日本では1988年に翻訳版刊行)の映画化。小説は汚れた現実とイノセンスな想い出の狭間を行き来する、裕福な子弟たちの刹那な日々が淡々と綴られる。
(*10)「人を好きにならなきゃ苦しまずにすむ」「人間は合流するのが怖い」「失ってしまうものを手に入れてみたい」など、最初から“すべてを手にしている”者だけが金と時間と引き換えに持たざるを得ない乾いた感覚。
- 中野充浩
文筆家/編集者/脚本家/プロデューサー。学生時代より小説・エッセイ・コラムなどを雑誌で執筆。出版社に勤務後、現在は企画プロデュースチーム/コンテンツファクトリーを準備中。著書に『デスペラード』(1995年)、『バブル80’sという時代』(1997年)、『うたのチカラ』(2014年)など。「TAP the POP」で音楽と映画に関するコラムも連載中。