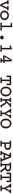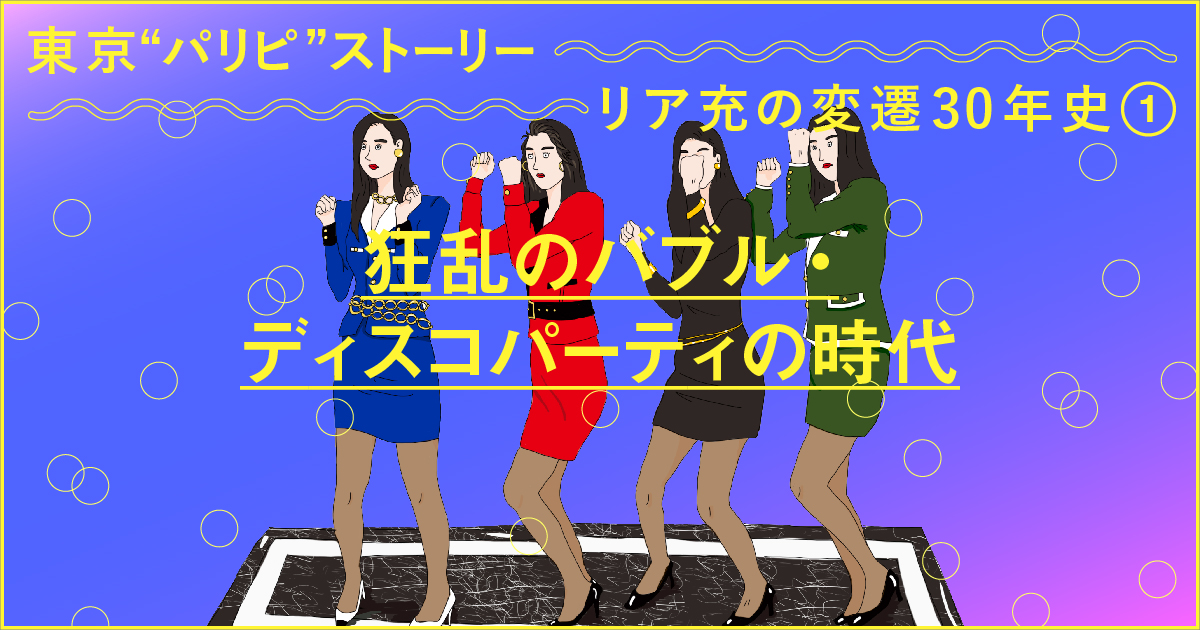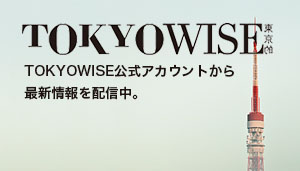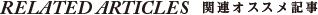2016.12.29
東京は、とにかくパーティ好きだ。
シーズン性やスペシャル感など何かと理由をつけては、毎週のようにいつも誰かがどこかで大勢のゲストを集めて、一時の祝祭やハッピーな出逢いを提供している。
そして、パーティは遊びの極致だ。
女たちが醸し出す“キラキラ”感、男たちが漂わせる“ギラギラ”感が入り交ざった空間では、互いの欲望を満たすためのスマートな会話や身だしなみが問われる場でもある。
パーティは、金の収支を気にかける主催者たちと、人生の楽しみに磨きをかける参加者たちが共有する華やかな都市文化の一つとして、今では東京ライフにおける必要不可欠なエナジー系コンテンツになった。
「パリピ」(パーティピープル)なる言葉が数年前から浸透し始めたが、それは物語全体においてほんの一章分にしか過ぎない。今回は時代ごとの主な事象を30年前から振り返りながら、その本質に迫ってみたいと思う。過去の流れや影響を知らずして東京のパーティ文化は語れないのだ。
TOKYOWISEで「Tokyo Pop Culture Graffiti~TOKYOに描かれた時代と世代の物語1983-2015」を連載中で、各時代のパーティ事情に詳しい中野充浩氏に話を聞いた。
──今回は東京のパリピ及びパーティの30年を振り返るという企画なんですが、中野さんが提示してくれた7つの時代区分に沿って話を伺いたいと思います。ではさっそく最初の時代から。
SCENE① 1986〜1991年
時代そのものが一つのパーティだったバブル時代
「東京の歴史上、最もリッチな青春」と謳われる数年間ですね。時代そのものがメガパーティと化して、享楽的になった若い世代が“リッチ&トレンディ”をドレスコードに、毎日のように東京中の遊び場へ繰り出していました。新しいもの好きで流行に遅れまいと消費を競い合う。ドラマや音楽、映画や雑誌もライフスタイルのための演出ツール。車も必需品。今の人からすれば信じられない話ですが、当時はごく普通のことでした。
──やっぱりみんなお金があったからですか? たった一夜のクリスマス・イヴも狂乱化して、“レストラン・プレゼント・ホテル”の3点セットが当たり前だったと聞きます。
今よりも若者人口が多かったので、街も店も情報もモノもすべてがこの世代の好みに合わせて変貌を遂げたことの方が大きかったと思います。ただの薄暗い倉庫街だった芝浦のような場所でさえ“湾岸ウォーターフロント”としてオシャレに生まれ変わったほどですから。
──バブル期と言えばディスコの時代ですよね? “ワンレン・ボディコン”のOL、高級なDCやインポートのブランドスーツを着たサラリーマンたちが踊っているイメージが定番です。
麻布十番マハラジャや六本木エリア、青山キング&クイーンや銀座Mカルロなど“お立ち台のある宮殿ディスコ”が全盛期に入った時代です。社会人は会社帰りにそのまま出向くのが日課でした。でも“ディスコパーティ”という観点では大学生が主役でしたよ。
──詳しくお願いします。
これは世代運命なんですが、今とは比べものにならないくらい競争率の激しい受験戦争の影響で、「大学生になったら遊ばなくちゃ」願望の強い人が増殖してマジョリティを形成していました。就活も空前の売り手市場なので、学生時代のキャリア醸成なんて夢にも思いません。“大学デビュー”と揶揄された遊びの初心者のほとんどは軟派サークルに加入していたので、こういう人たちを学校の枠を超えてネットワーク化した“イベント企画団体”が一気に力を持ち始めました。
──いわゆるイベントサークルですね。
六本木のディスコを複数店舗同時に貸し切る1万人規模の“合同パーティ”や、90年代になって“パラパラ”として浸透する上半身揃いの踊りを広めたのは彼らです。その動員力とPR効果に目をつけた企業から莫大な協賛金を得てビジネス化しました。ディスコパーティはもともと80年代前半に早慶の一部の遊び人たちがメジャーにしたものですが、バブル期で従来の企画重視から完全に営利目的へと変わったと言えます。
NEXT> 映画『バブルへGO!! タイムマシンはドラム式』で、劇団ひとりがその種の大学生に扮してクルーザーでパーティしていました。さて同時代の高校生は?!